
こんにちわ😄

今回の記事では「広背筋の柔軟性テスト」について、広背筋やそれら周辺の構造に基づき、そのテストが本当に「広背筋の柔軟性を検査するのか?」について考えたいと思います

「広背筋の柔軟性テスト」は広背筋の柔軟性をテストするのか?
広背筋の柔軟性テスト

広背筋の柔軟性をチェックするテストはいくつかありますが、代表的なものは以下のテストではないでしょうか

動画の様に胸の前で前腕同士を合わせ、そのまま真上に上げていきます

これでどの程度まで肘が上げられるかで「広背筋の柔軟性」をチェックします

このテストのやり方としては前腕を合わせて状態でやるのと、フォームローラーなどを使用してのやり方もあります

フォームローラーを使ってのやり方でも肘がどの程度上がるかを見ていきます

このテスト、日本語で「広背筋 柔軟性 テスト」と検索すると数多く出てきますが、英語で「Latissimus Dorisi Flexibility Test」と入力するとほぼ出てきません

その点から日本国内では一般的なテストだと考えられますが、英語圏ではその限りではないようです
広背筋の柔軟性テストの動き

上記の動画の様な広背筋の柔軟性テストには、さまざまな関節が関わります

一旦ここでどのような関節の動きが起きているのかを整理したいと思います
<広背筋の柔軟性テストで関わる主な関節の動き>
- 肩甲胸郭関節:外転(前方突出)、上方回旋、後傾、内旋
- 肩甲上腕関節:屈曲、水平内転、外旋、
- 胸鎖関節:水平内転、挙上、後方回旋
広背筋と周辺の構造

上記でご紹介したように「広背筋の柔軟性のテスト」にはさまざまな関節が関わります

関わる関節が増えるほど、その関節と関係がある筋肉も増えていきます

ですので、上記の関節の動きを基に広背筋以外にどのような筋肉が主に関わるかを考えていきます

肩甲胸郭関節の動きでは、主に大菱形筋と小菱形筋が関わるのではないかと思います

どちらの筋肉も肩甲骨の内転・下方回旋に関わり、「広背筋の柔軟性テスト」では伸長されるポジションとなります

肩甲上腕関節の動きでは、棘下筋、小円筋、大円筋、三角筋後部繊維、上腕三頭筋が主に関わるのではないかと思います

これら筋肉は全て肩甲上腕関節の水平内転で伸長され、屈曲でもほぼ全ての筋肉が伸ばされる位置になります

胸鎖関節の動きでは関わると考えられるのは僧帽筋上部繊維や鎖骨下筋だと思われます

僧帽筋上部繊維は胸鎖関節を水平伸展し、鎖骨下筋は下制するので、広背筋の柔軟性テストでは伸ばされる位置を取ると思われます

ただし、胸鎖関節に関わる筋肉でこのテストに関わってくる比率はそう強くはないのではないかと考えています
広背筋の柔軟性テストがテストするもの:考察

今まで見てきた様に「広背筋の柔軟性テスト」の動きではさまざまな関節や筋肉が関わります

それゆえに個人的には広背筋以外の要素によってそのテスト動作が制限されるということも十分考えられると思います

筋肉で言えば上記で述べたものは制限因子になりえますし、筋肉以外では肩後方の四辺形間隙周辺の軟部組織、肩後方や後下方の関節方といったものも十分制限要素になりえます

個人的な経験では広背筋以外の部位による制限の方が強いのではないかと考える機会が多いです

ですので「広背筋の柔軟性テスト」と言っても、広背筋だけではなく、「肩・肩甲骨周りの水平内転や屈曲時の柔軟性を大まかに見るテスト」という位置付けで考えています
まとめ

今回のまとめです!
- 「広背筋の柔軟性テスト」では両前腕を胸の前で合わせてそのまま上げていく
- この動きでは広背筋以外の筋肉や関節包といった他の制限要素も多く含まれる
- それ故に精確な広背筋の柔軟性というよりも、肩・肩甲骨周りの大まかな柔軟性のテストとして現状は考えている
今回のオススメ書籍

毎回解剖学に関するオススメ書籍を紹介しています!
脳振盪専門ブログのご案内

「しっかりアナトミー」の他にもスポーツ中の脳振盪専門ブログを続けています

ぜひそちらもご覧ください👇

店舗のご紹介

このブログの著者が経営している店舗のご紹介です

東京都文京区にてリコンディショニグ、競技復帰へのリハビリ、パーソナルトレーニング、脳振盪リハビリなどを行っています
セミナーのお知らせ

私が講師を務めるセミナーのご案内です



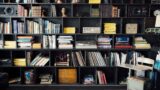


コメント